日出没にまつわるはなし
日出没が一番早い(遅い)のはいつ?
日照時間(太陽の出ている時間)は夏至の日に最も長く、冬至の日に最も短くなります。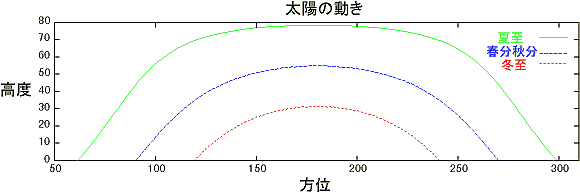
ところが、日出没の時刻となると夏至(冬至)の日に日出時が一番早く(遅く)、 日没時が一番遅く(早く)なるとはいえません。
それはなぜなのでしょうか?
私たちの使っている日本時は天文学上の言葉では平均太陽時と言われるもので、 実際の太陽の動きから得られる時刻(真太陽時)を平均化したものです。
これは真の太陽を基準にした時系の間隔が一様でないという重要な欠点を克服するためのものです。
[注釈]両者の差は均時差(=真太陽時-平均太陽時)とよばれ下図 のように変動します。 (通日とは1月1日からの経過日数の事です。)
☆真太陽時が一様ではないわけ
太陽の動きが一様でないのは地球の公転運動が楕円軌道である事(ケプラーの 法則により公転の速度は一定になりません。)と、地球の自転軸が公転面に対 して約23度傾いている(このため仮に黄経が一様に変化しても赤経は一様に は変化しません)事によります。
☆日常用いている時刻
日本時は厳密には国際原子時(TAI)にもとづく協定世界時(UTC)により定められ ますが、平均太陽時とほぼ同じものと考えて構いません。
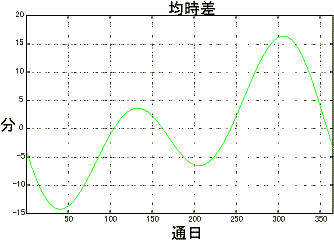
すると日出の真太陽時は12h - hr、 日没の真太陽時 は12h + hsになる事が分かります。
[注釈]したがって真太陽時で表した日出は、角度hrが大きくなる夏至の 日に一番早く、小さくなる冬至の日に一番遅くなります。
☆hr, hsの大きさ
太陽は地球の自転によって1日(24時間)でほぼ一回り(360°)するので、太陽が ある角度だけ運動するには角度/360*24時間かかります。 (例えば15°なら1時間かかります。)
つまり角度が大きいほどそれに比例して時間が長くなります。
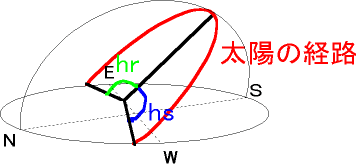
よって、
日出が一番早い(遅い)という事はhr+均時差が極大(極小)となる時 であり、
日没が一番遅い(早い)という事はhs-均時差が極大(極小)となる時 である
事がわかります。
なお、hr,hsは
aは太陽の高度で日出没の場合は定数、φは地点の緯度なので同一地 点では定数。δは太陽の赤緯で夏至には約23度26分、冬至には約-23度 26分、春分秋分では0度になります。
これを用いてhr、hr+均時差、および hs、hs-均時差をグラフ化すると以下のようになりま す。
(ただし、北緯35度東経135度、1999年で計算しています)
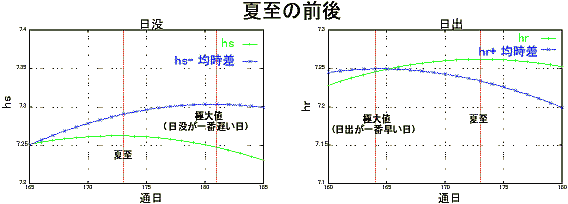
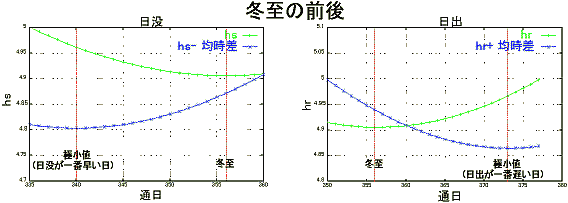
このグラフからわかるように、日出没の時刻の早い(遅い)日は夏至や冬至の日 と少しずれた日になります。
日出と日没で時刻の変化のスピードが違うのは?
これも均時差が原因でおこる現象です。先に示したように、日出は
ここで、例として冬至の付近の状況を考えます。
hr, hsは冬至で最小になり、1月の間は増加していき ます。一方均時差は1月の間は減少していきます。
このため日出時刻は両者の効果が打ち消し合って変化が小さくなり1ヶ月で10 分程度、日没時刻は重なり合って変化が大きくなり1ヶ月で30分程度変化する 事になるわけです。
東京と札幌、先に日が昇るのはどっち?
太陽は東から昇りますので、東に行けばいくほど日が昇るのは早くなるはずで す。札幌(東経 141°21′)は東京(東経 139°44′)よりも東にありますので、札幌 の方が日出は早いと思われます。しかし、東京と札幌の日出時刻を比べると 季節によって入れ替わっています。
| 季節 | 東京 | 札幌 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 夏至 | 04:25 | 03:55 | 札幌が早い |
| 冬至 | 06:47 | 07:02 | 東京が早い |
| 春分・秋分 | 05:44 | 05:37 | 札幌が少し早い |
地球は太陽の周りを約23度傾いた方向に自転しながら運動しています。
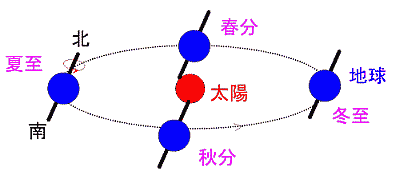
この図で、太陽に向いている面と向いていない面の境目が、その時刻に日出 (日没)のおきている地点になります。
| (1) 夏至のころの日出の様子 | |
|---|---|
|
同じ経度でも緯度の高い地域では既に日が昇っていますが、緯度の低い
地域ではまだ日が昇っておりません。
このように夏至付近では北極側が太陽の方を向くので緯度が高ければ高
いほど、日出は早くなり、日没は遅くなる事がわかります。 #特に、北極付近では日が沈みません。(白夜と呼びます。) 同じ時刻に日出になる地点を結ぶと右図のようになります。 |
|
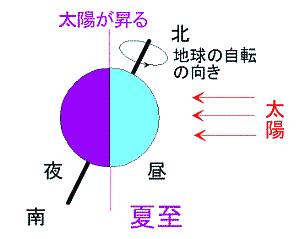 |
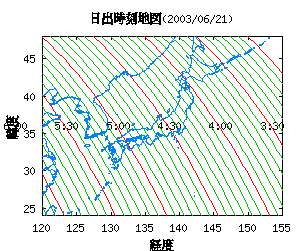 |
| (2) 冬至のころの日出の様子 | |
| 逆に冬至のころは、北極側は太陽と反対の方を向くので緯度が高いほど 日出は遅くなり、日没は早くなります。 | |
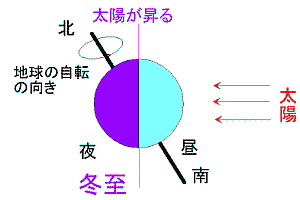 |
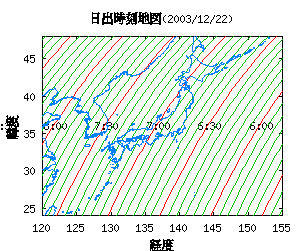 |
| (3) 春分・秋分のころの日出の様子 | |
| 春分・秋分のころは、北極側は横を向くのでほぼ経度だけで決まります。 | |
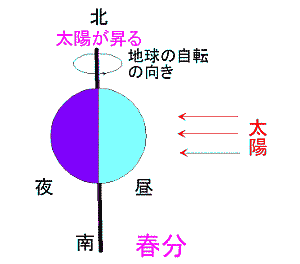 |
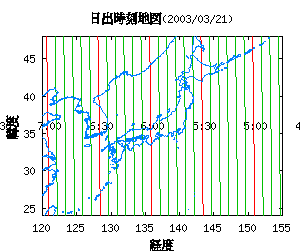 |
このように、季節によって日出の順序が入れ替わることになるわけです。
「春分の日」昼夜の長さは、同じではありません
1. 海上保安庁の日出没計算の目的
海上保安庁は、船舶等が洋上において天体を観測し、自船の位置を決定するために必要な航海暦(天測暦、天測略暦等)の編纂を行っています。航海暦を作成するためには、太陽、月、惑星及び恒星等の天体の運行を精密に予測し、その位置を知る必要があります。海上保安庁では国立天文台から提供される精密な天体暦のデータを基に、航海暦の作成や日・月出没の計算を行っています。
2. 春(秋)分の日の昼間・夜間の長さ等
春(秋)分の日は、一般的には昼間と夜間の長さが同じとなる日として知られていますが、実際には昼間の時間が長くなっています。例えば、東京における2000年の春分の日(3月20日)は、日出が5時45分、日没が17時53分、で昼間の長さは12時間8分となり夜間より長くなっています。 この理由としては、日出没の定義や大気による光の屈折等が影響しています。
日出とは、太陽の上辺が水平線(地平線)に接した瞬間、日没とは、太陽の上辺が水平線(地平線)に接した瞬間と定義されているため、 日出没ともに太陽の視半径分だけ、日出は早く、日没は遅くなります。(図1)
また、太陽の光が地球の大気を通過する際、屈折するため太陽が水平線(地平線)上に昇る前に見えるようになります。(図2)
このほか、観測場所の高さ(眼高)が高いほど日出はより早く、日没はより遅くまで見ることができます。(図3)
以上の理由により、日出・日没ともに約4分(計8分)昼間の時間が長くなっています。
3. 春分の日と満月の関係
春分の日は、19年周期で満月と重なります。 日本では2000年の春分の日(3月20日)はちょうど満月の日と重なっており、この19年後の2019年の春分の日(3月21日)も満月の日と重なります。19年の周期がある理由としては、1太陽年は365.2422日で、1朔望月は29.530589日ですが、この太陽年と朔望月の周期が、19太陽年(6939.602日)と235朔望月(6939.688日)でほぼ等しくなるためです。
ちなみに、東京における3月20日の月出は17時55分、月没は3月21日6時29分で、月の出ている時間は、12時間34分です。
